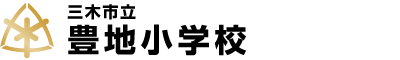避難訓練と1.17集会
1月17日(金)、阪神・淡路大震災から30年の今日、震度6を想定した避難訓練と1.17集会を行いました。
子どもたちにとっては、自分の身は自分で守れるようにする訓練、
教職員にとっては、子どもたちを安全に誘導するための訓練です。
そこで、地震の発生を休み時間に設定しました。
教室で友達とおしゃべりをしている子、運動場で遊んでいる子、廊下にいる子、
いろいろな場所に子どもたちがいましたが、地震の放送が流れるとすぐに身を守る姿勢を取り始めました。
運動場にいる子どもたちは、声を掛け合って運動場の真ん中に集まりました。
教職員は、安全に避難する経路を確認し、子どもたちを誘導しました。
けが人がいるため救護班も出動し、全員が安全に避難することができました。
1・17集会
今年は、地域にお住いの藤原様にお話をしていただきました。
藤原様は、三木消防署にお勤めされ、現在は兵庫県消防学校にお勤めです。
藤原様から阪神・淡路大震災に消防団員としていかれた時のことや能登半島地震のことを写真や資料をもとに話していただきました。
また、いつ起こるかわからない地震に対して今備えておかなければならないことも教えていただきました。
その中で印象に残ったことは、
自分の命は自分で守らないと周りの人を助けることができない
消防車がたくさんいても水がなければ火を消すことができない
家がつぶれたり、家具の下敷きになったりして亡くなる
阪神・淡路大震災の後、緊急消防援助隊ができた
ということでした。




お話を聴いた子どもたちは、
「今日のお話を聴いて、しっかり家族と話をしたいと思いました。」
「家具を固定していないので、固定したいと思いました。」
「水がなくなり、火を消すことができないことを知ってびっくりしました。」
「家具とかの下敷きになって亡くなる人が多いと知りびっくりしました。」
「避難所がどこか調べます。」
と感想を持つことができました。


藤原様へのお礼のことば
この後、全員で黙とうを行いました。
今日、家に帰った子どもたちは、家の中で地震が起こったときに安全に避難できるか、
避難場所はどこか、バラバラになったときにどこで集まるかなど、家族で話し合うことでしょう。
南海トラフト巨大地震が30年以内に発生する確率が約80%だと言われています。
地震に備え、防犯意識を高めたいものです。