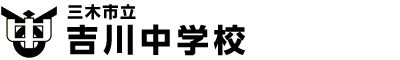☆今日の給食(4月21日)
今日の給食は、「たけのこご飯・牛乳・お祝いすまし汁・いちごクレープ」でした。

今日は、「進級・入学・入園おめでとう献立」でした。
三木市では、幼稚園の給食開始に合わせて、例年、20日前後に「おめでとう献立」を実施しています。
調理場では、朝から削り節でだしをとり、たけのこご飯の具をたきました。だしと生のたけのこの香りが
調理場に広がり、食欲をそそりました。(給食のだしは、いつも天然です。インスタントのだしは使いません。)
教室では、ご飯とたけのこご飯の具を混ぜ合わせてから盛りつけ、食べているクラスが多く、
「すばらしいご飯でした!」という最高の誉め言葉とともに空っぽになったご飯ケースを
配膳室に返却に来る1年生の姿に出会うことができ、こちらがお祝いしてもらったような
気分になりました。
【ちょこっと食育】 =神秘的な植物~たけのこ~=
たけのこは、竹の新芽です。竹は寒冷地帯を除き世界各地で育つため、
昔から、アジアを中心に世界中の人々の暮らしを支えてきました。
成長が早く、一日で1メートル近く伸びることや、何十年に一度しか花が咲かず、
咲くと同時に枯れてしまうことなど、一般的な草や木と異なる特性を持つ竹は、
人間にとって神秘的な存在でもあります。
たけのこの生産農家さんは、竹林の中を足の裏の感覚を頼りに歩き、狙いを定めると、
細長いクワのようなたけのこ専用の農具で、たけのこを掘ります。
また、毎年、竹林全体の成長を見ながら、「親竹」として残すたけのこを選びます。
親竹はあっという間に成長して竹になるものの、たけのこが収穫できるようになるまでは
2~3年かかるといいます。そこから5~7年くらいの間、毎年、たけのこが収穫できます。
そして、役目を終えたたけのこは切り倒され、イノシシ対策として竹林を囲む柵などに使用されるなど、
丈夫な竹は暮らしの中で長く活躍します。
まるで、竹林が人の一生のように次の命をつないでいるようですね。