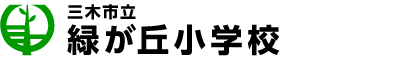リアル避難所運営+過去の災害から学ぶ 8.28
9月1日は防災の日。8月28日に地域の方のご協力を得て、リアル避難所運営訓練を行いました。
より実践に即すため、内容や流れをを知っているのは校長と担当者、コーディネーターの方のみで実施。
(昨年度のリアル不審者対応訓練、防災フェスティバルとも関連しています。)
今の学校の、そして教職員の防災に関するに認識やスキルの現状を自覚し、組織としても個人としても
今後に活かすのが目的です。活かす場は本校か?異動先?各地域や各家庭?災害に遭遇するのか?
等々、それはわかりませんが、災害はいつどこで起こるかわかりません。
今回取り組んだことが、どこかで何かにつながればという願いで実施しました。
そしてまだまだ暑い体育館で訓練スタート!!
コーディネータである又吉防災士さんの紹介、本研修のねらいの紹介、そして参加者どうしの
アイスブレーキングから始まりました。
今回の設定「今朝、大型の地震が発生、三木市全域に大きな被害。まもなく市民の方が避難が想定される。
リーダーを決めて対応してください。」
「鍵は?」「パーテーションやベッドはどこ?どうスペースつくる?」
日々の学校生活で意識はしていても、いざとなると全ての教職員が全てを把握しているとは限りません。
また災害時に熟知している職員が出勤できるとも限りません。


役割分担ができ、なんとなくみんなが動き始めたタイミングで・・
コーディネータの次のつぶやき
「避難の方が来られた。」
高齢で歩くのが困難な方、全盲の方、聴覚障害の方・・・(地域の方が役割を担ってくださいました。)
体育館はちょうど、物資運びのため人数が少なくなっていた瞬間でした。
→ リーダーの指示のもと再び役割分担



真夏の災害。要支援の皆様にはエアコンが効く部屋に再移動していただきました。

「ペットも一緒に避難。」

「この軒下がいいけど、崩れてくるかもしれない・・・。」
考えあう声が聞こえます。
そして、その間も居住地スペースづくりは続きます。


そこに「特殊電話の差込口は?」「応援物資の置場所」等々。
命を守る行動に「マッタ」はききません。知っているか否かで命運を分けることもあります。
みんなで知恵と力とチーム力を出し切りました。
ある程度の時間のあと、設置した段ボールベッドに寝てみたり、プライベートスペースに
入ってみたり・・・避難した場合の感覚を体験してみました。段ボールベッドは毛布が
あれば、さらに寝心地がよくなるそうです。簡易ベッドの方がいいなぁという声が大半でした。
第2部〈過去の震災から学ぶ〉
阪神淡路大震災、東日本大震災、能登地震・・・での様子や緑中の生徒も参加した
ボランティア活動の実際を動画とともにお話いただきました。

また、「〇〇ができません」や「□□ができます」等が即、記入できるグッズ
等を紹介いただきました。

災害が起こるたびに対策が行われ、少しずつは変わってきていることや
現地で何が大切なのか・・・知識や対応力とともに寄り添うことや
自分で自分が何ができるかを考えること、行動すること・・・
多くの大切なことの共有を図ることができました。
設定並びにコーディネートいただいた又吉防災士さん、ご協力いただいた地域の皆様
本当にありがとうございました。
みんなでみんなの命を守るつながりを、今後もよろしくお願いします。
この続きは、1月16日「1.17を忘れない集会」に実施予定です。
〈おまけ〉ペット君も無事に居場所が決まりした。

「自分できめる」「みんなと決める」~今日も「学校が楽しかった」~