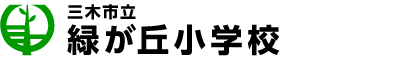先生たちも学び合い磨き合い(5) 8.28
8月28日(水)、全国学力・学習状況検査結果についての分析と
今後の取組について検討を行いました。
ご存知のとおり、本調査の内容は、5年生までの学習内容です。
良かったところは、どのような学習が効果的だったのか。
悪かったところは、何年生のどこでつまづきやすいのか。
質問紙からみえてくる本校児童の生活は、どのようなものか。
2学期から、全校でどんなことに取り組めそうか。
以前(かなり過去です)、「先生、問題、どこに書いてあるの?」と聞いた子どももいましたが、
本調査の問題を解くのに、かなり集中力や継続した根気が求められます。
(大人が真剣にやるとほぼ半分ぐらいの時間で解くことができますが、私は最近、このような問題に
触れる機会が少ないので脳みそが疲れた感がありました。)
既習事項の何を活かすのか、そしていろんな情報を関連付けて整理し、まとめて回答する力が求められるからです。
問われていることの核を読み解く力も必要です。
まずは「やってみよう」「読んでみよう」という気持ちが土台です。
何がきかれているかがわかれば、枝葉につまづくことなく、まっすぐ問題に対峙できます。
それができれば、意外と易しい問題もたくさんあります。
子どもたちと「なんや、そんなこときかれとったんか。」
「それやったらできるわ。」という時間が取れればいいなと思いました。
そして、今後の日常の学習の中で「〇〇のような▲▼をする機会を増やす」でなく
やることを明確に「◇◇を週〇回する」としていきたいと思います。
できている問題にもできていない問題にも今後の学習に向けてのヒントが
たくさんあります。
「『楽しいなあ、面白いなあ』と思いながら全校で続けて取り組めることはないか。」
6年間、9年間、それ以降等、長いスパンを見通しながら、今後の取組を進めていきたいと考えています。