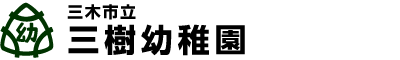楽しかった劇遊び ~実はエピソード4 思いは言葉に乗って・・・~
生活発表会当日の「はなのすきなうし」ラストシーンでは
マドリードから帰ってきたフェルジナンドと
フェルジナンドの帰りをずっと待っていたお母さんとが
次のような会話をしていました。

お母さん「おかえり!」
フェルジナンド「ただいま!」
お母さん「どこに行ってたの?」
フェルジナンド「遠いところ」
お母さん「大きくなったわね!
けがはない?・・・(フェルジナンドの身体を見て確かめて)大丈夫ね!
今日もいつものところに行く?」
フェルジナンド「うん!」
(二人で大好きなコルクの木の下へ行く)
お母さん「じゃ、みんなを呼ぶわね!
みんな~、フェルジナンドが帰ってきたわよ~!」
この温かい母牛と子牛のやりとりのセリフ、先生が決めた訳ではありません。
実は全部子どもたちが自然に作り上げたのです!!!
初めは「お帰り!」「ただいま!」だけで、
フェルジナンドが帰ってきたことも、特にお母さんからはみんなに知らせていませんでした。
それが、何度も役を代わり合って劇遊びをしていくうちに、
役になった子どもがその時の気持ちを言葉にし、
それが少しずつ他の子どもたちにも受け継がれていきました。
まず、「どこへ行ってたの?」と尋ねるお母さんが出てきました!
(突然連れ去られたわけですから、お母さんとしては尋ねたくなりますよね)
中には、「それは言えない・・・」というフェルジナンドもいたのですが(^^;)
最終、「遠いところ」という子どもたちの言葉になっていきました。
また、しばらくいなかったフェルジナンドの身体を気遣うお母さんも現れ、
「けがはなかった?」と尋ね、フェルジナンドの身体をいたわるようにもなりました。
そして、牧場に着いたフェルジナンドは、喉が渇いていたようで、
フェルジナンド役の子たちは、まず水飲み場に向かうようになり、
その姿をお母さんが真っ先に見つけてくれる!!!
そんな素敵な表現になっていきました。
そこからコルクの木へ向かうのも、
初めは先生が「コルクの木へ行きました」と言っていましたが、
いつしかお母さん自身が、「今日もいつものところに行く?」と言うようになりました。
(”コルクの木”と言わなくても、”いつものところ”で通じ合う・・・
子どもたち、絶妙の言葉のチョイスだと思いませんか?)
子どもたちの思いがふくらみ、積み重なってできたこの場面、
役になっている子はもちろん、それを見ているだけでも
”ああ、よかった”
”フェルジナンドはお母さんに愛されているな”
と幸せな気持ちになります。。。
だから、「みんな~、フェルジナンドが帰ってきたわよ~!」と聞いて、
出てくる牧場の仲間たちが本当に嬉しそうでした(*^^*)
*************************************
幼児期は、自分の感じたこと、思ったことを身体をいっぱい使って表現しながら、
心を満たし、仲間との共感を深めていきますが、
学童期に向かう、もうすぐ1年生になるすみれ組の子どもたちは、
身体表現から、言語表現の喜びも感じられるようになったのだなと
ひしひしと成長を感じました。

「はなのすきなうし」のフェルジナンドやお母さん、牧場の仲間たちのように、
”自分らしさ””その子らしさ”を大切にできる、
素敵なすみれ組のみんなです(^^)