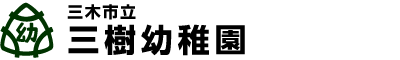三樹っ子アイテム・てんびん(2)
<三樹っ子アイテム・てんびん(1) からの続きです>
【令和6年度】
2年間、牛乳パックで作ったシーソー型のてんびんを使ってきましたが、担任は、いろいろ思うところがありました。
***********************************************
シーソー型だと、重さの違いは地面につくか、つかないかの違いのみになりがちで、分かりづらい。
もっと重さの違いが分かると面白いのではないか?
宙づりのてんびんだと、振り幅もあって、微妙な重さもはかれるのではないか?
また、可塑性があり、遊びの広がりも期待できるのではないか?
***********************************************
そこで、夏休みに職員で教材研究をし、新たなてんびんを創作しました。

こうして出来上がったのが、ハンガーを利用した吊るし型のてんびんでした!
夏休み明け、この新型てんびんをさり気なく年長児のクラスのテラスに置いていました。
すると、興味を持った子がいろんなものをかごに入れてつり合いを取ろうとし始めました!

三樹っ子畑で採れたオクラを量ってみたり・・・

前年度に引き続き、運動会の玉入れの玉の重さに興味を持ち、玉を量っている子もいました。
おや、腕を組んでハンガーの傾きを見ていますね!
そんな中、この年の年長さんたちはてんびんのつり合いを量るための大発見をしました!


もう一つの三樹っ子アイテム、「はかりんぼう」を使い、てんびんの重さを長さで測ったのです!
地面からかごまでの長さが、どちらも同じだと釣り合いが取れている、ということになります。

この方法を使って、後日、精米して袋に入れたお米が同じ重さになっているか、量ることもできました!
その時の年長さんの姿をその時の年少さんが見て、覚えていたため、
今年度の肥料作りに活かされたという訳です!文化の継承ですね(^0^)
それにしても、子どもたちはどうやって重さを長さで測るということを考えついたのでしょうか?
思い当たることとしては・・・
■吊るし型のてんびんにしたことで、地面からかごまでの空間が子どもたちに良く見えた
■普段から「はかりんぼう」で夏野菜の生長を地面から測る実体験があったので、”下から測る”という習慣が身についていた
でしょうか?
子どもたちの発想は本当に素晴らしいです!!